|
|
絵夢絶党名物 リレー式長期連載小説
連続大河小説
これ程に支離滅裂な話しは、かつて存在しただろうか。
複数の作者のうち、完結を目指した者は存在するのか。
人間関係を正確に把握していた者は、いや、
そもそも舞台がいつの時代だったのか、
何処の世界だったのか………。
この騒乱は誰にも止められない。(笑)
|
|
|
|
|
|
|
masadon 編
(1983年10月16日発行 Vol.21より)
|
|
|
|
西暦 現在+α、A国の国立極秘研究所では、秘密裏のうちにおそろしい計画が進行していた。その計画とは、物質瞬間移動装置を使って対立国であるB国の軍幹部を消し去り、最終的には全地球を征服しようというものである。この研究所は、その装置の製作から計画の企画までのすべてを行っているのだ。
「所長、装置が完成しました。」
「ミスが無いか調べろ!」
「了解。点検用コンピュータ switch ON!」
「No ERROR」
「所長、工ラーは発見されません。」
「よし、テストしている暇はない。直ちに計画に移る。」
「本部へホットライン、国防長官殿 プロジェクトAを実行します。」
「許可する。」
「まずは、B国空軍の長官から抹殺する。目的地をケンタウルス郡 ⛩星へ、周波数を標的に合わせろ!」
「了解」
「セット完了 プロジェクトA スタート3秒前 2、1…」
ここは ある国の ど田舎。一人の青年が日課の畑仕事をしていた。彼の名は浅田敏弘、24才独身であった。
『今日も暑いなぁ』
彼が抜けるような青空に目をやったとき、何かが彼の体を通り抜けたような感覚に襲われ、次の瞬間気を失った。
「所長、プロジェクトA失敗です。もう世界にあと3個しか残っていないZ-80が熱暴走をおこしました。」
「何だと、あれほど作動させるときは うちわであおげと言っておいたのに……」
「所長、大変です。方角決定用コンピュータ MZ-80Kが故障しています。」
「何? あれは、世界に2つとないのだぞ! せっかく私が組み立てたのに……」
「所長、B国空軍の長官が生存していることが判明しました。」
「国防長官にホットラインだ。長官、プロジェクトA失敗しました。修復不能です。…」
「ご苦労だった。」
こう短く言い切ると長官は研究所にICBMをぶち込んだ。

この続きを他の人が書くというのは どーでしょーか。
書いた人が次の人を指名する、いわゆる指名制でやってみませんか?
OKでしたら とりあえず咲田さん 続きをお願いします。
|
|
|
|
|
|
|
咲田 編
(1983年11月20日発行 Vol.22より)
|
|
|
|
何かまぶしいものを感じて目が覚めた。ひどく長い間眠っていたような気がする。まだ重いまぶたであたりを見わたすと、どうやらそこは森の中らしい。
「いかん!」
彼は重要なことを思い出した。
「うわっ! はっ早く二十日こんにゃく芋の苗を植えないと……」
が、そこは彼がまだ見たこともない土地であり、とうてい彼には帰るすべはどこにもない。いつまでも、こんなところに寝っころがっているわけにもいかないので、彼はとにかく人を捜してここがどこであるか聞き出そうと思った。
広い森である。もう、かれこれ3時間は歩いている。腹も減る。喉も渇く。しかし、妙な森である。見たこともないような、まるで[あじましでお]の絵のような植物ばかりである。ふと、彼は生理現象におそわれた。
「うっ!」
そそくさと1本の木の根元で、彼は用を足そうとした。
「のわ~~~ぁぁ!!! なんじゃこりゃあぁぁぁぁ……」
壮絶な叫び声を彼はあげた。
「ないっ、ないっ!」
どこへ遊びに行ったのか、彼の大切な1人息子が消息を絶っていた。と、同時に彼は己の身の大きな変化にやっと気がついた。
「胸がある!」
だいたい、1m80cmもあった身長が20cm以上も縮んでいる。
『悪い夢だ』
彼、いや彼女は思った。
『そうだ。ここで用を足すと、朝、布団が濡れることになるんだ。はっはっ だまされるものか!』
彼は、必死で自分を起こそうとした。つねった。たたいた。くすぐった。しばいた。が、努力もむなしく彼女は彼女のままである。彼女はあきらめた。第一、ぼーこーが限界を越えていた。彼女はその場にしゃがみ込み、生れてはじめての体験をした。
賢明な読者はもうおわかりであろう。すべてZ-80のしわざである。所長は、Mass Transportorの末端タスクにZ-80、及びMZ-80を使用した。これが、いけなかった。処理速度アップのため、Z-80 2.5MHzを4MHzで使用していたのである。ブロワーを付けなかったため、熱暴走したのだ。しかし、これがなぜ、浅田敏弘24才独身を女性にし、妙な森へトランスポートしたか…… このMass Transportor(以後 M.T.)は、被転送物を立体走査し、原子レベルで信号に置き換え、U-γ波にのせ、転送するという、S.F.ではおなじみの方法を使っている。(被転送物は転送完了確認後、反粒子波で消滅させる。)今回、Z-80の罪のない暴走により、浅田敏弘24才独身のからだは、Z-80の好みかどうかは知らないが、ある女性のものとなったわけである。
彼女は、わけのわからないままに、森の出口を求めて、さまよっていた。と、前方が明るくなって来た。
「やった! 出口に違いないわ!」(もー女になりきっている。)
彼女は足を速めた。
目の前には、大きな都市が広がっていた。
「町だ! 人がいる! 食い物も、水も!」
無我夢中で彼女は駆け出した。
町に着いた時は、もう日も暮れかかっていた。見慣れない人々が大勢歩いている。
「あの、すいません。ここは何という町ですか?」
「ここは、いったいどこなんですか?」
少し考えてから聞けばよいのに、御推察通り彼女は誰にも相手にしてもらえない。彼女が必死になればなるほど……。どうでもいいが腹が減った。もう長い間、何も食ってない。彼女は1軒の食堂の前で足をとめた。
「しまった! 金が無い。」
農作業に金を持って出るバ力はいない。しばらく彼女は考えた。
「こうなりゃ 作るしかない。幸い俺は女だ。」
ひらき直った空腹の女と御飯にたれた鼻血ほどこわいものはない。彼女は裏通りへと足を向けた。
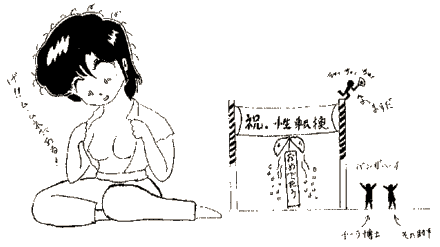
続きはN風ちゃん。お願いします。
|
|
|
|
|
|
|
N風 編
(1983年12月18日発行 Vol.23より)
|
|
|
|
しばらく来ないうちに ここもずいぶんかわってしまった。と彼は思った。地球からの捕給が来るたびに入り組んできている。彼は人目を気にしながら せまい路地へとはいっていった。ふと ひとりの風変りな身なりをした一人の女性がいる。と思った。瞬間彼の胸はキュン!と高なったのでした。なんと彼の初恋の人にそっくりなのです。璧に背をもたれてふし目がちにしているその子と目があうと、にこっ、とかわいく笑いかけられて思わず鼻の下がのびたのだった。
『いくらだろうか? 高いかもしれない。』
「やあ! β星は今もきれいだね。」
「……」
彼女は小首をかしげている。ここ流のあいさつを知らないところをみると別の星系からの移民者だろう。
「こんにちは!」
と彼女はまたかわいく笑った。だれも彼女が ついこの前まで男だったとは信じないだろう。彼女が女になったのはZ-80の暴走のせいだけではなさそうである。彼は女性のそばに近より軽く手をかけてたずねた。
「いくらかな?」
彼女はポッとほほを赤らめた。彼は
『うん きっとこの子は私を好いているにちがいない!』
「さあ行こうか」
……しかし彼は彼女が心の中で
『しめしめ、うまくひっかかったぞ』
と舌を出しているのにはむろん気付かなかった。それにしても彼女にとって気がかりなのは地球にそのまま残してきた農作物であった。それに加えやたらとおなかがへっている。
ピルルル……と彼の付けていたトーキー(けいたい無線)がなりひびいた。
「所長! たいへんです。マザーコンピューターのMZ-80Cのデータによると、この星全体に空間のひずみが発生しています。このまま行くと……この惑星は内部より崩壊してしまいます。」
「な なんだと! う~ん この大事な時に。わかった、今すぐ行く。」
『め、めしのたねが~。』
とあわてた彼女は、
「あ、あの 私この星のことまだわからないんです いっしょに行っていいですか?」
「う…う~ん、まあいいだろう。」
本格的におれにほれている。まあそれらしい服は着ていないし、だれもいかがわしい女だとは思わんだろう。彼は雑草の[ぬとぬと~る]や[ろひ~ぶの]に足をとられながらもお手々つないで研究所まで走ったのでした。
そうです。彼こそこの⛩星一番の物理料学者であり、また⛩教の宗主でもあるチーラ所長その人でした。所長といってもまだ彼はとても若く、研究や、その他もろもろにはげんでいるのです。
「これです。」
「う~ん たしかに空間がひずんでいる。M.T.の暴走だ。」
「はい 地球方向からのエネルギー放射をキャッチしたすぐその後でこの様になったのです。」
小じんまりとしたその本体のコンピューターにはいかにも研究所といった改造のしかたがしてある。画面にはときおりと言うよりはやたらとノイズが乗っている。彼女、いや 敏弘 いや 敏子はまじまじとそのコンビューターをながめた。
「いやー調子が悪いな。」
といってチーラ氏はコンピューターの横をこんこんとつついた。画面が正常にもどったと思う次の間にわけのわからないキャラクターでうめつくされた。
「いかん うちわだ! うちわ!」
と言っているうちに白いけむりがもくもくとのぼってきた。
「ど どうすればいいんだ!」
チーラ氏は愛人が交通事故にでもあったようなうろたえぶりである。かわいい声で
「わたしにまかせて!」
と敏子はちかくにあったはんだゴテとニツパをにぎりしめコンピューターのふたを開けた。
はたして ケンタウルス⛩星は崩壊の危機を乗りこえることができるのか がんばれ敏子! 運命は君の手の中にある………。
次回 阿閉センセの展開にご期待下さい。
これが絵夢絶党名物、連続大河小説の第1回~3回である。現在に至って十数回を数えている。しかし6~7回を迎える頃からライターが話の筋を完全に把握することができなくなり、矛盾や勘違いが続発するようになってきた。同一人物を別人物のつもりで話を進めたり、いたずらに何人も登場人物を増やしたりして収拾がつかなくなったりと、現在では誰が見ても支離滅裂になってしまっている。ここに紹介したのはそういった問題が起こる前の比較的まともな部分である。(編)
|
|
|
|
|
|
|
阿閉 編
(1984年01月22日発行 Vol.24より)
|
|
|
|
「ギャー」
思わず敏子は叫んだ。MZのふたをはぐったとたんに、何か黒くてべとついた昆虫らしきものが飛んできたのである。(恐らく物質転送機が暴走して運んできたその生き物は、メイド イン テラ だそうだ。)又よく見るとその生き物が数ヶ所でショートしていた。そのことに気付いた敏子は、博士の助手と協力して、その生物を追いだし、直し始めた。
その頃、異変は博物館でも起こっていた。遺跡から発堀された球状の物体がこつぜんと消滅したのである。
「やっと終わったわ。」
彼女はそう言って半田ごてを置いた。そして、チーラ氏の方に振り向いた。
「多分これでうまく動くと思うわ。さあスイッチを入れて。」
彼女は、以前にある回路を作って、スイッチを入れたとたんに破壊したことがあるのだが、今度は運でも良かったのか、うまく動いてくれた。それを確認すると彼女は、小さな声で
「おなかがすいたの。何か食べる物ない?」
と博士に言った。
「少し持ってくれないか。今はそれどころじゃないんだ。おい! 結果はどうなった。」
その声に反応して、
「今、表示します。」
と若くて美青年の助手がスイッチをONにした。
昔のSFとは違い、今は半導体を使用しているので、間髪を入れずに、正面のモニタがついた。
「おかしい。重力異常が全くなくなっちまった。」
それから、しばらくの間彼は、黙っていたが、何か思いついたのか、二言三言助手に何かわけのわからない事をしゃべったかと思うと彼女の方に向いて、
「さあ行こうか」
と話した。
「何がいい?」
自分の部屋に連れ込んだ博士は、彼女を改めて、見つめてなる程美人だと思った。彼の部屋はさっぱりとしたものだが、なぜか本だなの隅に裏から仕入れたと思われる[あずまひでお]の作品が居座っていた。この時彼女の心の中では激しい葛藤を生じていた。おもっきし食べたい。しかし女性としての見栄が……。
と、その時はげしい振動があったかと思うと、目の前に1mぐらいの奇妙な球形の金属質の物体が現われた。反射的に逃げだそうとしたが二人ともそれはできなかった。体が動かなかったのである。二、三秒もたったであろうか、我を取りもどした彼女は、その球に向かっていった。
「これ食べられる?」
その問を無視してチーラ氏は自分に問いかけるようにまともなことを言った。
「一体これはなんなんだ、それに体が動かん。」
「えっ、あなたがだしたものじゃないの?」
「わしゃ知らん。ひょっとするとまた転送機がぶっこわれたか。それにしても…」
その時二人の会話にもぐり込むように、頭の中に直接響くように重々しい声が聞こえた。
「すみません王女様、あなた様を驚かすつもりは全くなかったのです。私はついさっき目がさめた所ですが、あなた様はどうなされたのですか? この二百万年(ここはこの時わからなかったのだが、後になってわかった)もの間何も連絡なさらないで、心配しましたよ。」
その突拍子もない話に対して敏子は、こう答えた
「ちょっと持ってよ。私王女なんかじゃないわよ。私は平凡な一女性。あなた、なんか勘違いしてるんじやない? 一体あなたは誰?」
「そうですか人違いですか。そんなはずはないと思ったんですが、あなたと彼女は全く同じ細胞振動数なんですよ。」
暫く間をおいて、
「私ですか、私は王女様の警護兼、相談役です。王女様はとにかく我が種族のたった一人の生き残りですから…。」
「そんなこといったって私にどうすればいいってのよ。」
「それではいっしょに捜してくださいませんか?」
と安直な展開を見せ始めた。
|
|
|
|
|
|
|
阿閉 編
(1984年02月19日発行 Vol.25より)
|
|
|
|
彼(その球形のもの)が言うには、はるか二千万年もの昔 ある銀河系に、ある種族が存在し、一応支配していた。支配と言っても、この種族は、今の地球人と比べたら格段の差がある程、平和的なもので、武器をもっていても どうすることもできない時のみ使用するだけであった。しかし、その文化も、長くは続かなかった。ある科学者が偶然に生みだした超次元生物(細菌というかウイルスというか、その程度のもの)が、偶然にも、その研究室の外にもれてしまったのである。たちまちその惑星は全滅、なにぶんにも相手は、上の次元にいるから、それに気がつかなければ、宇宙船でもなんでも通過してくる。その生物は、食べる物(この変からすると細菌より大きなものだろうけれど。)が無くなるとしだいに絶滅していった。そして、生き残ったのは、外の銀河系に、一人で遊びに来ていたこの王女だけだろう。ということだった。
それから、地球という星に行って、遺伝子操作により、自分たちとそっくりな生物を作った。そして、その中で文化が進むのを見たり、他の惑星に調査しに行ったりしたのだそうだ。だが突然王女が消失した。ちょうどこの惑星で王女が、一人で宇宙船で彼から逃げた(たまに、気分が悪いとこういう風なすね方をなさるそうだ。)時、この辺が時空間のひずみみで、未来への道が開いていた為(彼も時間アナライザーで未来の10万年以上先ということだけはわかったそうだが)彼女をいつかわからぬ未来へと飛ばしてしまった。彼は追いかけようとしたが、どれくらい先かわからないので、とりあえず、10万年だけ未来に行き、それから今まで、じっとここで持っていたという事だった。
「それにしても、どうして私が、こんな事になったのよ。」
と敏子は、彼にきいてみた。
「そのDATAは私か王女様しか知らないわけですから、どう考えても、王女様に何か原因があるのではないかと思います。これは推測ですが、あなたが転移した時に、王女様が転移なされたとか。そのために、それがノイズとして乗ってしまったとか。」
とその時、その部屋についていたインターカムにスイッチがはいった。
「所長、銀河系政府からお電話(昔のなごりである。)がはいってます。何かあわてていらっしゃいますが。」
ここだけの話だが、銀河系政府の長官とチーラ氏はふるいつきあいがあり、本当は長官は無能なのだが、いつも、チーラ氏の助言でうまくいってるのだ。これがばれると長官はリコールされるので誰にも言わないように。
「うむ、わかった。今、すぐ行く。」
「失礼、ちょっと用事が出来ましたので、失礼させていただきます。」
そう言うと、急いで部屋を出て行ってしまった。
「一体何の用事かしら、」
ぽつりとつぶやいた。
「ちょっとお持ちください。今映像にうつしますから。」
そう言うと、彼は、球の一部から手のようなものをのばし、自分の体を開いて、その中から何かわけのわからない物をとりだした。それは、5cmぐらいのもので、目のような物がいくつもついていた。彼が操作すると、それから光があふれそして映像がでた。その間敏子は何も言わずにじっと見ていた。
「ああー、私だが、一体何かね。」
「今大変な事が起こったんだよ。同盟国であるはずのアルテミラ連合への通信が突然とぎれてしまったんだ。今調査船を送って調べさせたんだが、突然消息を絶ってしまったんだ。一体私はどうしたらいいんだ。あの国は知っての通り、近ごろでは友好的だったんだ。戦争をしかけてきたはずはないし……。」
この様な長いセリフを一気にしゃべった。
長官がこの後に言いたいセリフをわかっていた博士は、またかと思いながら仕方なさそうに、まためんどくさそうな表情を一瞬見せた。しかし長官は、自分の事だけを考えていたのでそれには全く気づかなかった。
「じゃあ、私が調ペに行くか。」
その言葉を待ってましたとばかりに長官は言った。
「そうか、君が行ってくれるのか、助かった。」
そして、すこし間をおいて
「君のことだから大丈夫だと思うけど、気をつけてくれよ。じやあ、頼む。」
そう言うと長官は連格を切った。
博士は、長官とのくされ縁もまだ当分続きそうだなと思いながら、
「さあ したくでもするか。また当分帰れそうにないな。」
そう言った。そして、自分の部屋に戻ってきた。その時彼女は、何も知らないふりをして、彼をむかえ入れた。
「お帰りなさい。どうでしたの。」(こう言うと、まるで新婚の妻の会話じゃないか)
「うむ、実は仕事ができてな。アルテミラヘ出張することになって、当分帰れなくなりそうだ。」(チーラ氏はのりやすいタイプだった。)
「じやー、一緒に連れて行ってくれない。料理や洗たくぐらいできるし、何かと役に立つかもしれなくてよ。」
その言葉に反応して、博士は、
「いかん、危険な旅に君を連れていくわけにはいかん。」
「それじや、彼も同行してもらうってのはどう。いいアイデアでしょ。彼なら、いろいろな事ができるでしょうし、」
二人の会話に割り込むように球形のものが言った。
「ちょっと待ってください。私は、まだ行くとは言ってませんよ。私には王女を捜す義務がありますし、ここを離れるわけにはいきません。」
「でも、彼女は、どこの空間に現われるかわかんないでしょ。ひよっとして、その星系にいるのかもしれないじやない。いなくても何か手がかりぐらいあるかもしれないし、それに、あなたが必要なのよ。ね、お願い。」
「そこまで言われると仕方ないですね。それじゃ行ってみますか。多分見つけられないとは思うんですが。」
博士を無視して話が進んでいた。
「おい、おい、まだOKはだしてないつもりだぞ。うーん、どうせ、連れて行かないと言っても何とかしてついてくる気だろう。わかった、好きにしなさい。」
とうとう博士はあきらめてしまった。
「きゃー、博士大好き。」
そう言うと彼女は、抱きついた。
彼女の様な美人が抱きついて悪い気がするはずもなく(彼女はまだ元が男である事を言ってなかった。肉体が変化したのは言ったのだが、さも自分がもとは女であるという風に言ったのである。)博士はそのままじっとしていたかったのだが、球形の彼が、しゃべった。
「お取り込み中すいませんが、船はどうするつもりですか。よろしければ私のをお使いになりませんか。」
「そうね、彼ほどの文明の持ち主の船なら、きっとすごいわよ。」
「そうしようか。じや私は出発の用意をするから、君達も用意しなさい。」
というわけで話は転回を見せております。こういう設定になってくるといつまでも続けられるでしょう。このストーリーもはやくも5回、最低1年はもたせましょう。来月はE-Power選手にバトンタッチです。がんばってください。
ところでこの話では敏子がまだ何も食べていないように書いてしまいましたが、実はあの球体がしゃべっている間に食べたのです。どうもすいません。
|
|
|
|
|
|
|
E-Power 編
(1984年03月18日発行 Vol.26より)
|
|
|
|
敏子は、あの球状の物体をアンバー(UNB.[Universal Ballの略])と、名づけた。敏子が頭にフッと浮かんだ名前であった。アンバーは王女につけてもらった名前があった。偶然にも、王女がつけていた名前も、アンバーであったのだ。アンバーは、大変不思議に思ったが、ただの偶然の一致であろうと思った。
チーラ氏、敏子、アンバーは、出発の用意も万全で、一路、銀河系第二⛩惑星、アルテミラ星、科学技術庁本部へと向かった。
現在の宇宙は、西暦2000年(絵夢絶党という左翼派が、地球という惑星を治めていた時代)当時のものとは、考えもつかないくらい、変わっていた。
太陽系の惑星は、すべて消滅してしまっている。とくに、人類が住んでいた唯一の星である地球は、西暦5×××年、コバルト爆弾の爆発により、崩壊したとアンバーは記録している。だが数名の絵夢絶党メガロポリス支部員の新惑星開拓グループが、海王星の2つの衛星を開拓しようと宇宙ステーション⛩に出張していた。このため、人類の絶滅は、免れたのであった。西暦7×××年には、残りの太陽系惑星が一直線に並び、太陽からの何らかの、電磁波が、各惑星の中心を通り、音もなく一瞬にして滅びた。それと同時に各衛星も滅びてしまった。太陽系には、太陽と、宇宙ステーション⛩と、ハレー彗星以外何もなくなった。
人類は、⛩で子孫を増やし続けたが⛩の収容人数の限界を越えようとしたとき、もと地球が存在したところに、地球そっくりの惑星ができていた。人類は、すべてその惑星に移り、その星をケンタウルス⛩星と名づけた。何故⛩星ができたのか、長年の間、不明だったが、太陽系内にさらに惑星が誕生するプロセスを見て解明できた。なんと、76年周期のハレー彗星が1回転するたびに、同一の場所へ、星のちりを投げ捨てて行くのだ。これがくりかえされて大きな惑星、⛩星そしてアルテミラ星をつくったのだ。人類は、アルテミラへも移動し始めた。そして文化を形成していったのだ。
そして、第3の新惑星ホーマルハウトMilky星が生まれ、人類が移動し始めた。太陽系という名称はなくなり、銀河系の名称のみが残ったのだ。
⛩星には、A国、アルテミラ星には、アルテミラ国、Milky星には、B国ができ、何百万年も平和であったが、現在は、A国が、プロジ工クトAをすすめるため、アルテミラ国と同盟を結んで、計画を実行しているのだ。
以上のことが宇宙の歴史として記されている。
ところが、球体アンバーには、以上の歴史のほか、細菌が、ある惑星を滅ぼしたことが記憶装置に記録されてある。このことは、どんな歴史書にも記されていない。だが王女の存在が確かであれば、アンバーに記緑された歴史も確かである。
一体これは、どういうことなのであろうか。
現在、全世界にZ-80は、5個は、確実にある。
⛩星のマザーコンピュータMZ-80CとサブコンピュータのMZ-80K。これらはオン・ライン(えっ うそー ほんとっ!!)で、アルテミラ星のMZ-80K2とつながっている。Milky星では、MSXのPASOPIA IQを、惑星支配コンピュータとして使っている。
アルテミラ星では密かに、80KBのMSXをつくっていた。
これが、なぜかMilky星のMSXとつながってしまったのだ。
このため、空間のひずみが発生するなど全世界に異常を起こしてしまったのだ。あるいは、もともと異常であった世界をさらに異常にしてしまったのであろうか。とにかく世界は非常事態なのだ。どこかの国がさらにMSXをつくると人類の3つの星は、すべて消滅するかもしれない。MSXが人類撲滅につながるということを、だれも気づいていない。Z-80は5個だけしか確認されていないが、いつ6個目が確認されるかわからない。いや、確認される前に人類は撲滅しているかもしれない!
世界は非常に危険な状態なのだ。
チーラ氏らは、何も知らず、アルテミラへと向かっている。
世界の異常の原因をつきとめることができるのであろうか。アンバーの船はもちろんコンピュータ制御である。もしやそのコンピュータはMSXではないだろうか!
人類の運命は、いかに。また、アンバーと王女の母国の正体は。敏弘が変異して敏子になった本当の原因は。……一体、何であろうか!!
今回は、世界の回想場面でしたので、話はあまり進みませんでしたが、謎が少しは解明したのでは、ないでしょうか。
今回は6回目だったのですが、次回は、だれに、バトンタッチしようかなぁ。
masadon氏と咲田さんはTOKYOへ行っちゃうし…。阿閉さんは、2回書いてるし…。
で、結局、N風先生、意外な展開をみせて下さい。
あとをヨロシクおねがいします。
|
|
|
|
|
|
|
N風 編
(1984年05月20日発行 Vol.28より)
|
|
|
|
アルテミラへ向かう船の中で 敏子の胸は高なっていた。べつにバストが大きくなったわけでは無く心臓がドキドキしていたのである。思わず敏子はチーラの腕を抱いた。チーラ氏は一瞬戸惑ったように赤面したがすぐに敏子にほほえみかけ、
『大丈夫だよ』
と言うかのようにうなずきながら彼女の肩に手をかけた。何故か室温インジケーターが高温側にふれたがまたもとにもどった。そのとき敏子はコンソールパネルの中央部にあるプレートに目がいった。
「あらっ あの[MSX]てあるパネルは何なの?」
「な、なんとこの船はアルテミラやMilkyで開発されたというスーパーコンピュータを載せているのか…?」
チーラ氏は
『ぎょえ~』
といった表情でそう言った。
「ああ、これですか…」
アンバーは体からマニピュレータをのばしてプレートをくるくる回転させた。
「実はねじがゆるんでるもので……」
そういって[XSW]と固定した。
「でも スーパーコンピュータであることはちがいありませんよ。実はこの時代には2つとないであろうと言われる6502という化石を使用しているのです。」
「な……っ われわれの星に伝説として伝わるあの6502…ですか 空からおり立ち禁断のリンゴを食べて地にはびこったという…」
[禁断のリンゴ]という言葉に敏子の胸はしめつけられたような思いがした。手のとどかない記臆がそうさせたかのように思えた。アンバーも少なからず動揺していたように見えた。
「で…伝説ですか……この6502は第2小わく星郡の中のシリコン濃度の高いいん石の中で見つかったものなのです。さいわい紫外線もよく当たり、環境がよかったので、シリコン成長率も良くうまく化石化しています。」
「う~んなるほど」
チーラ氏は感心した。これではわれわれの誇るZ-80以上かも知れないと思った。
そのときピルル…ピルル…と警告音がなり中央のディスプレイに何かが写った。
「あれ何かしら。」
と敏子が言うのとほぼ同時にチーラは
「移動機雷だ」
とさけんだ、
「う~んこのままではアルテミラ星にはいれないぞ」
「だいじょうぶです。私にまかせて下さい。」
といってアンバーはコンソールのスイッチにふれた。船がゆったりとゆれはじめた感じがしてこまかな加速、減速がはじまったのがわかった。スクリーンを見るとプロ級のゲームプレーヤがプレイしているような感覚におそわれた。こうなるとZ-80顔まけの感がある。あわや! と思う事数回であったがなんとか機雷をぬけた。円窓から外を見ると宇宙クジラが泳いでいた。
「わっ、クジラだわしっぽをあんなにふってるわ。かわいい。」
敏子は両手をかるくにぎり口もとをかくした。
「ああ、今ごろがさかりなんだ」
ごていねいにもアンバーはスペースポートに船をつけた。チーラ氏はあわてふためいていたが閑散としたポートには他に船がなく、何者も攻撃してこなかった。いったい何がアルテミラ星に起こったというのだろうか。
「アンバー、どうも様子が変だ、このあたりは辺ぴだとは言え活気のある町だったはずだ……そうだ このままこの町の研究所に行ってみよう。何かわかるかもしれない。」
「ねえ、どうでもいいからこんな陰気な所はやく出ましょうよ」
「はい、では船を変形させますので……」
コンソールに向かいつつそういうと船はグォ~ンという低い音とともに地上車に変形した。もともと大きな船ではなかったが車となると少しばかり大形であった。
「では、行きます」
走る地上車から外をながめているとこの星のいたる所にあるといわれる女神の像が見えてきた。数回見てはいたがこんなに間近に見たのは初めてだった。…その時チーラ氏はあぜんとした。敏子にそっくりなのである。
「こ…これは、アンバーいったいどうしてなんだ」
「こればかりは私にもわかりません、この星系に長らくいますし 王女様をさがす手がかりになるのではとさぐってはみたのですが…ぐうぜんなのかもしれません」
敏子は自分に似ているといわれる女神を後方に見ながら一言
「ふ~ん、似てるの…」
と言った。チーラ氏は目まぐるしく展開するできごとに何かの関連性を求めていた。
ほどなく研究所についた。そこは[化石CPU発掘研究所]となっていた。車からおりた2人と1つはドアに手をかけようとした。その瞬間背後から声がした。
「ワナにひっかかったようだな」
手にビ-ム・レイをもったプロテクターに身をやつした数人がせまって来た。
もうわけのわからない展開であります。これでもずいぶん悩んだのですよ。
次は、みたびの阿閉先生におねがいします。
注)誤字、脱字がもしございましたら、人に気づかれぬ様自分で直してください。
|
|
|
|
|
|
|
阿閉 編
(1984年06月17日発行 Vol.29より)
|
|
|
|
「だれだ。」
そう言いながら、チーラは振りかえった。半秒程遅れて、敏子も、それに続いた。
「お前達が、帰ってくるのを持っていたのさ。」
その中の一人が、まるで西部劇にでてくる、悪漢の決まり文句のような事を言い放った。その男は、三人を値踏みするように、じろじろと、見た。特に、敏子に対しては、いやらしい目つきになっていた。
「これは一体、どういう事なんだ。君達は、一体何者なんだ。それに我々をどうするつもりなんだ。」
チーラは、少しでもこの星の状況を把握しようとしているのだった。
「詳しい事は、ボスのところで聞くんだな。」
そして、敏子が、きょろきょろと、目だけを動かしているのに気が付いて、
「おっと、妖しい真似はやめてもらおう王女さん、君達は、大事なお客様だ、手荒な真似はしたくない。」
その時敏子とチーラの頭の中に、アンバーの声が響いた。
『王女様、チーラ聞こえますか。これから、会話は、思考によって行ないます。話したい事があれば強く念じてください。私が媒体にもなりますから。わかったら、YESと念じてください。』
二人はほぼ同時に返答した。その後、アンバーに質問したのは、王女であった。
『アンバー、彼等は、一体何者なの。彼らをやっつけられない。』
『彼らは、どうも王女様を待ち伏せしていただけの様子です。以前に、王女様がこの星に立ち寄ったらしくて、その時、何かがあって、王女様を神とあがめたらしいです。それが、この星の宗教の基盤になったようです。彼らが知っているのは、この程度で、詳しい事は、全くわかりません。』
そして、
『もっと情報を得る為には、彼らのボスという存在に会わなければなりません。ですから、ここは、おとなしくするのが一番じゃないですか。』
アンバーが全て話し?終えるのを持って、チーラも、何か聞こうとした。
『町に住人がいない…』
その話を中断する様に、男が命令した。
「じゃあ皆さん一緒に来てもらいましょうか。」
そう言って、仲間に合図を送った。すると三人の男が彼らのわきに、二人の男が彼らのうしろにまわった。まるで、連行されているようであった。
彼らは、車で、ある建物についた。その建物を見て、チーラは、一言、
「ここは、政府庁じゃないか。」
と声にあげた。
車は、(車と言っても、今とは違いリニアカーで、車の中は、かわいい女の子の写真がペタペタはっていた。)地下駐車場へと入っていった。そして、一般議員には止められそうもないような場所で停止した。車の横には、エレベーターがあり、全員乗った。てっきり上の階に行く(一応その建物は地上部がメインであった。)のだろうと考えていたチーラは、地下へ移動するのに驚いた。しかも彼が知る限り、この建物に、地下十階というものは存在しないはずであった。敏子は、元が男であった為であろうか、この様な状況におちいっても、少しも、恐怖感をいだかなかった。チーラは、それを見て安心したが、少々ものたりなかった。エレベーターに乗っていたのは、30秒か、1分かははっきりしなかったが、とうとう着いた。地下72階、地表から360mの位置であった。一体この場所は、何だろう。敏子は考えていた。
とびらが開いた。男たちに命令(やんわりとした口調で)されて、チーラたちは、走行ベルトに乗った。そして、一般人立入禁止地区と書かれている場所を通って、一つの部屋にきて、そこでおりた。その部屋の前には、警備員がいたので、男は、何事か、こそこそと話し始めた。その時、走行ベルトを何気なくちらっとふりむいたチーラは、彼の知りあいに似ている男が通過するのに気が付いたが、何も知らないふりをした。
そうしているうちに男は戻ってきた。ドアが開いたが、そのドアは、厚さが、50cmもあり、どんな攻撃にも耐えられそうである。ドアを通過し、秘書室を通って、何者かの部屋に入った。
次回は石原センセにおねがいします。
|
|
|
|
|
|
|
石原 編
(1984年07月15日発行 Vol.30より)
|
|
|
|
「ようこそ」
と その男はジャン・ギャバンのようなドスのある声で言った。これに対してチーラは
「これはどういうまねだね? アンタがボスか? 納得のいくように説明してもらおうではないか…」
と(なんとしても敏子を守りぬくぞ! という気負いで)少々興奮ぎみに言った。
「無礼なまねについては どうか気になさらんでほしい…」
この一見温厚な対応にチーラは面くらった。
「王女様にお手伝いしてもらいたいことがあるので わざわざ御足労願ったわけです。」
「アタシに手伝いを? 何を手伝えとおっしゃるのですか?」
と敏子は男まさりの声で聞いた。
「実は先月、ここからペーの方向に120kmの地点で6800が発見されたのです。」
[6800]という言葉を聞いてチーラは思わず大声で
「6800が見つかったって!? あの6800が…」
「そうだ、あの6800が地下300inchのシリコン採掘現場から3個見つかった 内2個は完全なセラミック・パッケージで、1個は足のないムカデの形で発見された、そこでもっと発掘してみる価値がある、それには民の労動力がどうしても必要だ、それで民を王女様の鶴の一声で集めたいのだ…」
このとき突然アンバーが沈黙を破って思考に割込んできた。
『王女様、チーラ、この男はどうやら あの究極の6809を手に入れたいらしいです、それで大規模な発掘隊を組織するつもりなのです。それから……おや この男急に心を閉ざしました、思考を読まれない術を知っているようです。一層警戒したほうがいいようです…』
チーラは一瞬ハッとした、
『そうか、それでヤツが…アルファ・ガンマがここにいたのか…』
『チーラ、そのアルファ・ガンマって誰です!?』
とアンバーは聞いた。
『さっき、この部屋に入る前にすれ違ったヤツだ…アイツはかつて俺の仲間だった イイヤツだった… アイツの専門は68系の発掘と研究だった。しかしアイツは6809の魔力に魅せられて…』
『魅せられて それでどうなったの?』
と敏子は興味津々だった、
『それから蒸発してしまった…』
とチーラはちょっと悲しそうに言った…
「ところで王女様、私の願いを聞いてもらえますか…」
とボスは言った。
「ちょっとまって 少し考える時間がほしいわ…」
敏子は時間かせぎをしようと思った…
えー 今回はこのへんで どうもきたねー字でスンマセン…
次回は、夏休み中なのでフレッシュマンのmasadon氏にバトンタッチ!
|
|
|
|
|
|
|
masadon 編
(1984年09月23日発行 Vol.32より)
|
|
|
|
「まあ そうですねぇ。御来しになってすぐお呼びしましたから、さぞお疲れのことでしょう。お答えは明日で結構ですから今晩ゆっくりお考え下さい。部屋は部下に用意させてありますから…」
とボスは言った。
えー 先月おとした上にまことに申し訳ないんですが時間がないのでお次の咲田さんにまわします。咲田さんなら3~4枚は書いてくれるでしょうから…
|
|
|
|
|
|
|
咲田 編
(1984年11月18日発行 Vol.34より)
|
|
|
|
まったくひどい話である。少なくとも敏子が今ここにいるということはチーラのおかげなのだ。だが、今チーラが案内された部屋はどうみてもたこべやである。不潔なベットが4つと明滅しているLight Tubeがあるだけで、あとは[おまる]があるだけだ。御丁寧なことにたったひとつのドアには鍵までかけてあった。
『いまごろ敏子の奴はふかふかのベットにころがっているんだろうなぁ……』
などと考えていると無性に腹が立ってきた。しかしそんなこともいっていられない。事態はお世辞にも良いとはいえないのだ。謎の地下空間、消えた人びと、そして謎の男……。アンバーは敏子とコンタクト中らしく、チーラの問いかけには応答してくれない。まっ、とにかくアンバーがReady状態になるのを待とう。そう決めてチーラは横になった。
一方敏子である。チーラの想像通り、彼女の案内されたのはVIP用の部屋らしい。いつの間にか付き添いの女性が2人、彼女の世話役としてついていた。勿論ベットは丸八の羽毛ふとんである。
「プリンセス、お着がえのまえにお風呂にお入り下さい。」
ギク!! 確かにここ数日風呂になんか入っていないだけに入りたいのはやまやまだが、よく考えてみると彼女はまだ自分の裸をみたことがないのである。怖い! 嬉しい! 彼女は返答に困ったが、どうやら返答の必要性はないらしかった。2人に連られて入ったのは超音波風呂でもウォータージェット風呂でもなく、浴槽式のものであった。
「こんな旧式の風呂がなんでこんなところに……」
敏子はつぶやいた。
「プリンセスのために作らせたものです。クロンメリン様の趣味らしいですけど……」
1人が答えた。
「さあ…」
「あっ、あっ、あっ!!」
というまもなく彼女は一糸まとわぬ姿にされてしまった。敏子は自分のすがたを見る勇気もなく必死に視線をそらそうとしていた。気がつくと2人も全裸になっていた。
「プリンセス。どうなさいました? 鼻血が出ていますよ。」
「もうおのぼせになったのかしら……」
敏子はあわてて鼻をつまんで言った。
「チョッ、チョコレートを食べすぎたものですから。」
それを聞いて2人は横から敏子を支えるようにして浴室へと入っていった。敏子はやたら自分の下半身が気になった……が、その必要のないことに気づいたのはまもなくのことであった。
さて、そのころアンバーは……単に寝ていた。なにか策があるというのであろうか。一人、船の中で自分のタイマースイッチをセットしてパワーを切ってしまっていた。
翌日である。敏子はいかにも王女らしいいでたちで、チーラはいかにも情ない姿で男の前に引きだされた。
「プリンセス。さっそくでなんだが返事は決りましたかな?」
「……『アンバー! 何やってんのよ!!』……えっ、ええ。いちおう。」
ぎこちなく敏子は答えた。
「そっ、その前に一つ聞いておきたいことがあるわ。」
「何ですかな?」
男はおっとりとした口調で言った。
「私にこの星の人びとを動かしてほしいとおっしゃったけれど、肝心の人の姿が見えないのはどういうわけかしら?! 私はまだこの星にきてからコンタクトスーツ(白兵戦用の皮膚密着型セーフティスーツである。)を着た人以外には一人も会っていないけど……。」
苦しまぎれに敏子はこんなことをいった。
「……市民はちゃんといますよ……この地下都市の第8エリアから第113エリアにね……」
男は答えた。
「地下都市ですって?!」
『そのとうりです。』
アンバーが割り込んできた。
『この星の全住民がこの地下都市に現在住んでいます。』
『どういうことだ!』
チーラが訊ねた。
『ミユー汚染です。』
「ミユー汚染!?」
殆ど同時に2人は叫んだ。
「御察しのとうりですよ……」
男がいった。
「もうかなり進んでいます。地上はもう一週間と人間は住めません。なんだかヤマトチックな話かも知れませんが、我々アルテミラ人が生きのびるには何としてもあと4つの6809、できれば68B09が必要なのですよ……。時間がありません。早くしないと6809もミユー粒子で殺られてしまいます。……プリンセス!!!」
一気に事の全貌をきかされてキョトンとしている2人にアンバーが話かけた。
『少なくとも今この男の言ったことには、嘘はありません。後の采配は貴方がたに任せます。』
そう言うやいなや、アンバーは2人の思考から抜けた。数秒の沈黙ののちに敏子が答えた。
「承知したわ。」
不賢明な読者の為に説明せねばなるまい。一年前、アルテミラに巨大な彗星が大接近した。が、この彗星のイオン化した尾によってアルテミラの電離層が破壊され、大量のミュー粒子が降り注ぐようになったのである。前以てこの現象を予知していたアルテミラ政府は星ぐるみでこの地下都市を建設し、一億を越える人びとが一年前からここに住んでいるというわけである。
「有難い! 感謝しますぞ、プリンセス。」
「……しかし、一体あなたは何者なのだ!! アルテミラの官僚にあなたのような人物がいるという話は聞いたことがない。」
チーラが無視されまいとして口をはさんだ。
「おっと、これは失礼、チーラ博士。」
「わっ、私をしっているのか?!」
|
|
|
|
|
|
|
N風 編
(1985年02月17日発行 Vol.37より)
|
|
|
|
男は口もとに不敵とも思える微笑を浮かべた。
さて、大きな展開を見せた大河小説 これからどうなるのでしょう。来月は……私が書きます。すいません。
|
|
|
|
|
|
|
N風 編
(1985年03月31日発行 Vol.38より)
|
|
|
|
(今までのあらすじなので省略いたします:編)
ととと……残念ながら 今月はもう書くスペースが無くなってしまった。う~ん非常に残念だ……。
ではまた来月。ごきげんよう!
|
|
|
|
|
|
|
N風 編
(1985年04月28日発行 Vol.39より)
|
|
|
|
この男こそアルテミラの影の支配者と言えるメイ・シーンその人であった。男は自分の考え通りに事が進みそうなので非常に晴れやかな顔をした。
「わたしの名は、メイ・シーン。新しく役職についたばかりなので知られないかも知れないが…。ところで、やってほしい事がもう1つある。実はこの人物なのだが……」
といってメイ・シーンは一枚の立体写真を取り出した。立体写真と言えば[とび出すヌード]でおなじみで思わずチーラは身をのり出してしまった。
「おっと失礼……、男ですなあ…年齢は25歳…独身といった所でしょうか…」
「あっ」
敏子は突然声をあげた。
「どっ どうしました?」
「いいえ……な なんでも……」
「この人物に見覚えでも…」
「いいえ……ただ美形だったものですから……」
敏子は心臓が高なるのを覚えた。別にその青年が美形だったからではない。なんとその写真は敏子がまだ敏弘だった時の顔にそっくりであったからである。
「それならいいのですが……この人物は反乱分子のリーダーなのです。」
「反乱分子?」
「ええ、彼はもう数個のZ-80を手に入れています。ここでもし彼が6809を手に入れたなら……その時は革命が起こるでしょう……」
メイ・シーンは うしろをふり返り、葉巻きに火を付けた。ため息とともに紫がかった煙がもれた。
「彼と接触をしてほしいのです。我々はもう顔が知られている。あなた方は⛩星出身という事は彼等にもわかっているはずだ。彼がZ-80で何をやっているのか、6809はもう発掘したかどうか探ってほしい…」
『アンバー、アンバー』
敏子はアンバーによびかけたが返事が無い。
「はっはっは…アンバーに呼びかけは通じない。」
メイ・シーンはコンソールのボードに触れた。…壁のパネルにはアンバーが何本もの支柱に固定されていた。画面全体が異常に青かった。
「い、いつの間に……」
チーラは歯をくいしばった。
「さっきあいつと思考通信をしただろう。シールドが甘いのだよ。アンバーはその通信のあと捕獲してある。」
メイ・シーンは一転して態度を変えた。
「彼……いや名前はトジアというのだが……接触をしてもらうが へたな動きをするとアンバーは分子に崩壊する事を忘れないでもらおうか。」
「貴様、アルテミラ政府の人間ではないな……」
「いやチーラ君…今では私が政府そのものなのだよ……それとは知られずに支配する……最高の統治だとは思わんかね。なあ お姫様」
と、彼は敏子のスーツをはぎとった。
「あっ。」
敏子の美しい上半身があらわになった。
メイ・シーンの正体が安直にあばかれ脈絡もなくトジアなる登場人物が出てくる。さて、この大河小説は一体どうなるのか?
わしゃ知らん! 次回阿閉君に期待しよう。
|
|
|
|
|
|
|
阿閉 編
(1985年06月23日発行 Vol.40より)
|
|
|
|
「いや! やめて!」
言葉とは裏腹に、これから起こりうるであろう初めての体験、男性には絶対に味わえない未知なる出来事に、胸ときめかす敏子であった。(噂によると、敏子のモデルになっている○○氏も、マゾだそうな。)
「やめろ! 彼女には手を出すな! もしも、彼女の×××を、御前の×××で、××××でみろ、ただではすまさんぞ!」
チーラは、彼女をものにするのは、自分のはずだ!。きっとこれは、仕事に忙殺され、ストレス及び、フラストレーションの溜まっているN風氏の陰謀に違いないと怒った。が、彼は体を動かすことが、出来なかった。彼が行動を起こすと気付くや否や、メイ・シーンは、ボタンを押したからだ。チーラの頭上から光線が降ってきて、チーラの神経をまひさせてしまったのだ。
二人の思いが渦巻き、そのわずかな時間が、30秒程(実測)の時間に感じられた。
「う-ん。いい臭いだ。とても香ばしい。」
メイ・シーンは、そのスーツに顔をうずめると、そう言った。
「やっぱり、成熟している女性の方が、良いものだな。私には、全くロリコンの気持ちがわからん。」
そして、呆けている彼らの顔を見ると、
「おー。じゃあ二人共行ってくれないか。君達の事だから、拒絶はしないと思うが、念の為に、このブレスレットをはめてもらおう。二週間のうちにこの仕事をやりとげないと自動的に爆発することになっている。はずそうとしても無駄だから、あきらめて、仕事をはたしてくれたまえ。」
そう言うと、彼らにブレスレットをはめた。敏子は抵抗しても無駄なのがわかっていたので、音無くなすがままにさせておいた。ただ、一応恥らいもあったので、片手で乳房を押えていたが。
メイ・シーンは、わざとらしく、
「おーと、すまない。君にはこの服は似合わない。」
そう言うと、指をパチッと鳴らし、
「あの服に着がえてくれ給え。」
男が持って来た服を敏子は受け取った。
「隣の部屋に必要なものは全てそろっているはずだから、あと2時間までに、出発する準備をして、待っていてくれ。」
メイ・シーンはドアを開けた。
「かわいいよ。」
そう言い残すと部屋を出て行った。
ドアが閉まると、チーラの呪縛がとけた。彼はくずれる様に床に倒れた。ごつんという音がして彼は気絶してしまった。
「大丈夫!。しっかりして!。」
彼女はチーラの体を起こすと体を揺った。しかし、彼が目覚める気配が無かったので、彼をソファーの上に運んで行った。そして、彼女はあきらめて、隣の部屋に、着替える為にはいっていった。
その部屋には全ての物が揃っていた。化粧品から下着までどんな種類もありそうだった。シャワールームもあったので、彼女は、まず、シャワーを浴びる事にした。すっぽんぽんになり、シャワーを浴びた。思わず鼻唄を歌い始めた。あそこにシャワーがかかると、彼女は、快感を覚えはじめた。が、右手のブレスレットを見ると我にかえり、急いで髪を洗い、ドアを開けた。バスローブに身を包み、髪の毛をふいていると、いきなり、この部屋のドアが開いた。そこには、チーラが立っていた。
彼女は驚いたが、それ以上に驚いたのは、やはり、チーラの方だろう。彼はまひしている時から意識が無く、この部屋が一体何なのか、全く知らなかったのだ。そして調べようとドアを開けたとたん半裸の敏子が立っているではないか。安物のエロビデオみたいなストーリー展開は無く、彼はあわてて、
「すまない。」
と言ってドアを閉めた。
15分後位で彼女はその部屋から出て来た。敏子は、可愛らしいパンティーをはいていたが、チーラには、それがわかるはずは無かった。ホットパンツに露出部の多いシャツといういでたちで、彼女のスラリとした足や、きれいなはだが強調されていた。
「さっきはすまない事をした。」
「いいわ。それよりこの状況は何とかならない?。」
チーラは、彼女にも自分と同じブレスレットがはまっているのに気づいた。
「その前に、このブレスレットは一体何だ。君は知っているかい。」
彼女は、チーラが知らないのに気づいた。
「これは、時限爆弾だそうよ。二週間のうちにここに戻って来ないと、爆発するらしいわ。はずそうとしても無駄だって言っていたわ。あきらめて、彼の言う通りにするしかないみたい。」
チーラは、これの事を言っているところで失神したのか。と思った。
「あと20分くらいで、彼が来るらしいわ。こちらに武器でもあれば彼を人質にして、こちらの言う通りにでも出来るかもしれないけど…。」
「うむ、しかし、奴が本当に黒幕かどうかの保障も全く無いのだよ。果して、自分の正体を明らかにする人間がいるだろうか。自分の正体を完全に隠して置くからこそ、誰にも知られないのだし、それとも、この仕事がすんでも、我々を無事に開放してくれないのかもしれないな。」
敏子は、彼の洞察力(被害妄想かもしれないが。)に驚いた。そして彼を尊敬した。
『それよりも大事な事は、奴の本当の目的が、一体何なのかだ。なぜ、自分の部下を変装させて調べないか。スパイを作りあげるのくらい簡単なはずだ。我々を使うのは、どんな理由があるか、又は、どんなメリットがあるのだ。』
「我々は、中立な立場で調べていくしかなさそうだな。一応、彼らの言いなりになっておいて…。そのうち、両者の目的もわかるだろうし、それにこれもあるから。」
彼は、ブレスレットを敏子に見せた。が、彼らはアンバーのことをまるっきり忘れていた。
そのころ、アンバーは、彼らの言葉を聞い?ていて、がっくりしていた。彼は何と言っても超技術の産物。こんな物くらい全く大したものでは無い。(彼の本体は、ここには無く、又、これくらいのシールドにしても、彼が生まれる数百年以上前に出来ていた。)ただ、超小型の盗聴機を送り込んで、特殊な電波(通常空間を流れないもの)を流していたのだ。彼は逃げても良かったが、しばらく二人のなりゆきにまかせておいた。
「またせた。」
ドアが開いて、メイ・シーンが入って来た。
「さて、来たまえ。」
そう言うと、彼は、二人を屋外に連れだした。そこは、飛行場になっていた。そして、その中の小型飛行艇を指さした。
「あの飛行艇を使って、彼らと接触してくれ。」
「そして革命が起こる、つまり彼らが、6809を手に入れた時は、取り返してくれ。」
メイ・シーンは、そのまま中へと戻っていった。
残された二人は、仕方なくその飛行艇の中に入ってみると、座席にアタッシュケースが置いてあった。チーラが、あけてみると、トジアに対する資料と、地図でいっぱいだった。しかし、その中に紙切れが一枚はいっていた。それには、こう書かれていた。
[ハグが本当の敵だ、私は彼に操られて]
チーラは、つぶやいた。
「アルテミラの中央大コンピューターが、どうして……。」
私は全く責任はとりません。あとは煮るなり焼くなり、好きにしてください。
次回は、石原氏です。
|
|
|
|
|
|
|
石原 編
(1985年09月15日発行 Vol.42より)
|
|
|
|
「うーむ」
チーラは悩んだ。
「しかし、今はそんな時ではない。一刻も早く、トジアについての情報を収集しなければ……」
「でも、この飛行艇、えらく旧式ね。」
と、敏子はぷりぷり。確かにとんでもない代物だった。が、どうにもならないことは明らかだった。タイムリミットは336h後である。
かれこれ、140時間が経過していた。政府庁のある所からアルテミラ星の裏側であった。10時間前に発った処で、仕入れた情報によれば、あそこに見えるカラシメンタイ市で、トジア・バジーナ反乱軍首領に会えるはずだ。情報提供者によれば、[バーガーズ・ドリアーガ]で、合言葉は[ザップ!]であるらしい。
「さて、ここがバーガーズ・ドリアーガだな。敏子、入ろうか。」
「ええ、合言葉は[ザップ]よ。」
そこには、客は誰もいなかった。カウンターの奥には、凄く可愛い女の子(レッシーちゃんみたいな子…)が、営業用の笑顔で言った。
「いらっしゃいませ。私、アレッシーよ。私を指名してね。」
これを聞いてチーラはあ然としてしまった。だが、敏子は慣れたものである。
「お前は、ザップよ!!」
と言うやいなや、どこからか現れた男二人に、銃を突きつけられた。
「坊やもお嬢ちゃんも、大人しくしているんだね。さぁ、向うに行ってもらおうか。」
彼等が連れて行かれた部屋は、地下7階にあった。そこには敏子そっくりの優さ男がいた。
「エ一ッ!」
思わずチーラは叫んでしまった。
「お黙り! 坊や。ほう、お嬢ちゃんの方は私とそっくりだね。」
と、不気味に言った。
「私は、何世代にもわたる優性遺伝操作によって生み出された。遠い昔、この壮大な計画が別の惑星にも移されたと聞いている。お嬢ちゃん、君もそうかもしれないな。」
「何よ! お嬢ちゃん、お嬢ちゃんなんて。私はレディよ。馬鹿にしないで。大体なによ、その何とか計画って?」
「なかなか威勢がいいね。まぁ、いいだろう。この計画はね、この世界を治める人間を造り出す為の、偉大なものなのだ。今や、機は熟した。だから、私は反乱を起こすつもりなのだ。いずれ革命が起こるだろう。」
チーラは、ゴクリと唾を飲込んだ。
「ではトジアさん、既に6809/68B09を手に入れていらっしゃるのですか?」
「勿論。こちらには駒が揃っているのだ。無いのは王女だけだ。勝算は十分にある。」
「なるほど、しかし我々は6809を奪うように要求されている。さもなければ、このブレスレットが爆発しておしまいになってしまう。」
「ハッハッハー。メイ・シーン、そしてハグ。そんなことは先刻お見通しだよ。」
チーラと敏子はあっけにとられていた。
「どうして…?」
「フッ、そんなことはどうでもいい。君達には、この6809を持ち帰ってもらう。」
こういうわけで、6809を渡された二人は政府庁へ戻ることになった。この6809がトジア・バジーナ等の手によって、ALUのロジックの一つが破壊されていようとは、二人は知る由もなかった。タイムリミットまで192h。
が、この二人は不運に見舞われた。メイン・工ンジンの故障であった。フューエル・インジェクションがイカれていた。万事休すかと思われたが、トジアの協力によって50h後に、なんとか復旧した。タイムリミットまで142h。
帰りの飛行は最悪だった。ハリケーンを迂回した為に、政府庁に着いたのはタイムリミットまで22mだった。
エア・ポートには、メイ・シーンが出迎えていた。
「首尾はどうだったかね?」
この高慢な態度にムッとしたが、と同時に内心こう思った。
『ヘッ、いまに革命軍が貴様のようなダニ野郎をギロチンの血錆にしてくれるわ。』
「さぁ、渡して貰おうか。無いとは言わせないぞ。」
時間が追っていた。爆発までそんなに余裕はない。チーラは、素直に6809を渡した。しかし、メイ・シーンは一向にブレスレットを外す素振りをみせなかった。
「オイ! 約束通りこいつを外して貰おうか。」
と、チーラは狂ったように言った。
「君達、お人良だね。それは、ただのニセ物だよ。チーラ君はともかく、敏子君はまだまだ使い道があるからね。」
と言うと、彼は声高らかに笑った。
「貴様ってヤツは、どこまで汚いんだ! 地獄に落ちてしまえ!」
「下品な野郎だ。伍長、この二人を別々に監禁しろ!」
こうして再び地下奥深くに監禁されることになってしまった。
ハーイ! 今回の連続大河小説は、いかがでしたでしょうか? エッ? 面白かったって!? それはどうもありがとう。このお話し、一挙に終結へと向かいそうな気配をみせましたが、さて次回は如何に? E-Power氏の好演出に期待しましょうね。
では、今回はこのへんで。さようなら……
|
|
|
|
|
|
|
E-Power 編
(1985年10月27日発行 Vol.43より)
|
|
|
|
二人は、地下の奥深くに別々に監禁されてから、数日が過ぎた。
チーラ氏は、体の調子が悪くなりつつあることに、気付いた。生まれつき、彼は、体が丈夫ではなく、昔から、よく病気をしたものだった。しかし、薬学の発達により、病気を感じさせる中枢をマヒさせる薬が、チーラ氏がまだ幼い頃に発明され、彼はそれを極めてひんぱんに服用した。その薬は体を楽にさせるが、体への負担がかかり副作用も人によってはあらわれるという欠点があった。チーラ氏は、そのため、体が弱くなってしまったのだ。さらにチーラ氏には副作用まで働いた。ところがその副作用というのは、生きている間は決して病気をしないが、死期が近づくと、病気をしなかった分がまとまって徐々に病気をし出すという作用である。その病気というのも、人によって違うというのである。
チーラ氏はもしかすると死期が近づいているのではないだろうか。もしそうならば病気というのはどんな病気なのだろうか。
話題はさらに展開してしまいました。連続大河小説は、まだまだ終結へ向かうことはないのではないでしょうか。
次回は、阿閉さんにお願いしようと思います。
|
|
|
|
|
|
|
阿閉 編
(1986年03月16日発行 Vol.45より)
|
|
|
|
敏子は、チーラとは違った豪華な部屋に閉じこめられていた。12m×15m×5m程の大きさの部屋の天井からは、数千万クレジットもしそうなシャンデリアが吊され、人間数人なら中に楽々入れそうなマントルピース、部屋の真ん中にはアンティック調のテーブル、そのまわりには身体が沈みこみそうなふかふかとした椅子が6脚あり、そしてまわりの壁には、なんと女性の肖像画ばかりかけられていた。
「一体どういうつもりなのかしら。」
敏子は最初唖然としていたが、メイ・シーンはただの女好きなだけだろうと納得した。
一時間程もその部屋でボケーッと座っていただろうか。彼女はやっとある事に気が着いた。その絵の中で一枚だけやけに目新しい物があったのだ。彼女は近づいて良く観察してみた。それは今は無き元祖地球の20世紀頃の服装をしたショートカットの可愛い女性であった。敏子はその顔をじっと見つめていた。
「うーん。どこかで見たことがあるような気がするんだけど……。」
暫らく考えていたがまるっきり思い出せなかったので、遂に諦めて他の絵をながめてみることにした。実はこの女性が今回の事件に深く関わっていた事に気が着くには、まだ三日必要だった。
それからまる一日が過ぎ去った。彼女はあれから一度もメイ・シーンと顔を合わせることは無かった。さらに部屋の外でも時折り物音がするだけで至って静かだった。
「そろそろ食事の時間だわ。」
敏子は脱走の計画を再確認した。この部屋には盗聴器も隠しカメラも一切無かった。しかも食事を持ってくるのは若い執事一人きりで、外には誰もいなかった。わなかもしれなかったが、このまま待っていたところでらちがあかないのだ。
『失敗して元々、成功すれば儲けものだわ。』
と彼女は考えていた。
彼女は部屋の外をのぞいた。あたりに人影は全く見られなかった。
『うそみたい』
そう思ったがうまくいったのだ、彼女は深く悩まない性格だったのでそれ以上なにも考えなかった。そして部屋に気絶した若い執事と食事を残したまま、外に出ていった。
「それにしても、ここはどこかしら……。」
敏子は10分程この階を歩きまわったが、上に行く道も、下に行く道も見つからなかった。たった3部屋しかないこの階の全部を調べてだ。
「こういうつもりだった訳ね。たとえ部屋から抜けだせてもこのフロアから出ることができないようになっているって事ね。」
『お困まりですか。』
彼女が振り向くと、パンが浮かんでいた。ぼうぜんと立ちつくしている敏子に対してさらにそれは話した。
『この階から出られないのでしょう。』
『……。ひょっとして、あなたアンバー?』
『ご名答!。それよりこれからどうするつもりなのですか。何か脱出する手段でもあるのですか?。』
『それが無いから因まってるんじゃない。なんとかならないの?。」
『なぜかその階付近だけ透視できないのです。おそらくESPバリアでも張られているのでしょうが、これだけの文明で開発できるとは思えないのです。誰か他の星の人間が手を貸しているのじゃないでしょうか。とにかくそのバリアが張られている限り私もうかつに手が出せないのです。ですから自力で途中まで脱出してください。』
そう言い終わるとそのパンは彼女の手の上に乗った。
『ふみゃあ。そんな事言ったって、ここからどうやって出るのよ。』
その時目の前の壁が動いたようだった。
「まさかね。」
しかし誰が見てもすきまは拡がっていった。彼女は急いでパンをズボンにしまい、物陰に隠れようとした。
「隠れなくてもいいわよ。私はあなたの味方よ。」
壁は完全に開いた。やはり作者の趣味だろうか若い女性だった。しかも敏子に体形か似ていた。
「詳しく説明している暇はないけど、あなたと入れかわるために来たの。反乱軍にはあなたが必要なの。協力して。」
『信じてもいいかしら。』
敏子はアンバーに聞いてみた。
『いいんじゃないですか。このままこうしていても時間の無駄ですから。』
ゆっくりと敏子は出ていった。
「それじゃあ、この基地の外で待っている仲間が情報をくれるから、すぐに逃げて。あっとその前に服を抜いで私の服と替えてちょうだい。」
その女性は早口にしゃべると、服を脱ぎ始めた。仕方がないという顔で敏子も脱いでいった。しかし色気も何もない光景だった。こういう場面でなければ、なかなかおもしろいだろうが……。
そうこうしているうちに二人は服を取り替えあった。
「ここから抜け出すにはこのレーダーを利用して! 見ればわかるから。」
その女性は腕時計のようなレーダーと何か書いてある紙を渡した。
「急いでここから離れて。」
それがその女性との最後の会話となった。壁の中に入ると自動的に璧が閉まっていった。
敏子は紙をみた。紙には要所要所の機械の操作方法等が書かれてあった。その中の最初のこの部屋の機械の操作を見た。ボタンを見るとどうも移動ルームらしかった。紙のとおり[SHLD22]と敏子は入力した。するとすぐにその部屋は上方に動き出した。
『でもチーラはどうするの?。ねえアンバー。』
『ひょっとすると彼らが助けるかもしれませんから、うかつな事はしないほうが良いと思えますが。どちらにしてもそれは脱出してからにしたらどうでしょうか。脱出できる保障でもあれぱ話は別なのですが。』
『そうね。しかたないわね。』
それからまるまる2時間もかけてやっと外に出られた。割にあっさりと出られたのに不審に思ったのはアンバーだけだった。またもや敏子はラッキーにしか感じていなかった。
「えっと、ここをまっすぐに300m程行ったところの赤い車に乗る……。えーっとあれね。」
急いでそれらしい車に近づいていった。中にはまたもや若い女性か待っていた。
「早く乗ってください。これから支部に向いますから。」
その女性は、車を急いで発進させた。
「私達の知らべたところでは、実はメイ・シーンは誰かに繰つられているか、脅かされているのではないかという結果が出たのです。」
敏子は唐突に本題に入られたので戸惑って、その女性の話をただ聞くだけだった。
「ですからその後にいる者が誰であるのか知らべて欲しいのです。」
『あっ、そう言えば確か最初にメイ・シーンから受け取った紙に何か書いてあったわ。あれを調べれば何かわかるんじゃないかしら,』
そう考えたが口にはしなかった。
そこにたどり着くまでに日は暮れてしまった。ちょうど50km程度の距離に思えた。その家は結構大きかった。そして向えに来た男を見て彼女は驚いた。なんとチーラだったのだ。(ハッハッハッ。怒らないでね。)
話しはますますややこしくなるばかり、さてこの収拾は誰が着けますか。お楽しみ。さて次回はS風さんにお願いします。
ついでに一言
今まで書きませんでしたが、実はアンバーは製造ナンバーが001です。出した限りは責任は全て僕に有ります。ですからくどくもこのキャラタターを出演させていたのです。どうもすみませんでした。
|
|
|
|
|
|
|
TURBO 編
(1987年02月08日発行 Vol.51より)
|
|
|
|
「おかしい、なにか、おかしい。」
チーラはつぷやいた。そして、まるで牢獄のような作りをした部屋の中で、じりじりと迫り来る何物かわからない恐怖に耐えきれずに気を失った。まぷたに、敏子の姿が浮かんできた。だが、その顔は笑顔ではなかった。
「にあわないよ、その顔は。笑顔が一番よくにあう!」
そう言おうとした、しかし、いえなかった。敏子が振り返り歩いていく。行かないでくれ、僕を一人にしないでくれ、このままでは、このままでは、このままでは……
チーラは、敏子が歩いていく先にかすかに光り始めた物、いや人をみつけた。それは、暫くたつ内に、まばゆいばかりの光となって、チーラを照らし始めた。
「あっ、あのひとは!」
「お前か、早くも来てしまったのだのう。なぜだ、私が操作を誤ったからなのか?」
「いいえ、どうかわかりません。たぷん僕の遺伝子が何か劣性因子を持っていたからだと思います。しかし、あなたがいるということは、ここは?」
「そう、おまえの思っている通りなのだよ。おまえがこんなに早く来るべき所ではなかったのだよ! しかし、不思議だのう。おまえが女に導かれてくるとは。」
不思議だろうな、とチーラは思った。これまで、女を愛しているといっても言うだけだった。また、くさるほど女は寄って来た。しかし、誰一人として満たしてくれなかった。敏子は違う、あんな女は始めてだった。
「なに、にやにやしとる。早く来ないか!」
「はい、すみません、ソ・チーラ様」
「えっ、何故、こんな所にチーラがいるの?」
敏子は驚いた。なぜ、ここにチーラがいるのだろう。確かに、チーラは捕まっているはずだ。また、だまされたのか。
「ようこそご無事で、お帰りくださいました。われら一同あなたさまの下部です。」
「なに、チーラ、何故、私にそんな事を言うの?」
「私はチーラであっても、チーラではないのです。」
敏子にはわからない事ばかりであった。
「つかれたでしょうから、とにかく中でお休みください。」
ぐっすり眠りたかった、しかし、敏子にはチーラの不可解な行動が気になってなかなかねつけなかった。
「コ・チーラ様、ア・チーラ様の生存反応が消えました。」
「やはりか、すぐに遺体を探しだせ。そして、彼の体についているキャラクター・レコーダーとサイコ・レコーダーを回収してこい。」
「とうとう、この日が来てしまったか。どれ、私も合体の準備をしなければ。」
コ・チーラは、静かに本棚の前に立ち、ある本をとった。それは、⛩教の創始者であるソ・チーラの書いたものであった。
「えっと、ド・チーラの項は、250ページだな!」
てなわけで、暫くの間休載させていただいた、この連続大河小説ですが(作者多忙のため)、今回、新たな執筆陣を多数揃えましたので、これからのおそらく100回を越えるであろうこの作品にご期待いただくようお願い申しあげます。
前回の作者、阿閉氏のご指名はS風氏でありましたが、阿閉氏の再指名により、ふつつかながら若輩者である私ことTURBOが筆をとらさせていただきます。(要するに、どんな話になってもわたしゃしらないということです。)
さーって、この話どうなりますことやら。次のご指名は平田君におまかせしようかなー。これで少しは恋愛小説らしくなっただろう。なんのこっちゃ。
|
|
|
|
|
|
|
Y風 編
(1987年12月発行 Vol.58より)
|
|
|
|
どれほどの時間がたったのだろうか。敏子はようやく目を覚ますところである。Dr.チーラと再会できた安心感のためか彼女は 星を出発してから初めて眠ったような気がした。目をあけた敏子の前には見知らぬ部屋が展開していた。
「ここはどこ…」
ひっかかるような声しか出なかった。部屋の中は薄い桃色のもやがかかったように光で満たされている。いたるところで発光していた。つまり、部屋の壁、床、机etc.が全てみな僅かに光っているのだった。敏子は唯一光のないベッドから起き上がり、じゅうたんに降り立った。足はくるぶしのあたりまで埋まってしまった。
『毛のおおい動物の上に立ったという感じだわ』
と思った。
『まあなかなかの物ね、この変な光さえなければ』
一通り敏子が部屋を見渡したとき、女性が入口に立っていた。
「お目覚めですか」
それは、メイ・シーンから逃げ出したとき同行していた女性の声であった。背はそれほど高くないが、背筋がピシッとしていて、
『なかなか手ごわいぞ』
と敏子は。…いや久しぶりに敏弘の声でそう思った。かおだちはいわゆる才媛タイプで半ば男性をバカにしているという雰囲気を持っていた。目は少しあがりぎみ、目の間隔はやや狭く、形の良い鼻がきれいな直線を描き、厚めの口唇に到っている。
「私はリネル・シラム。あなたの世話係をトジア・バジーナに言われました。わからないことがあったら聞いて下さい。答えられる範囲で答えますから。」
「ここは一体何処なの」
一番気になっていた質問をした。
「ここはアルテミラの地下都市の中心セルスです。多くの人々がこの箱」
リネルは部屋を見回して
「…の中に押し込められている。全てがオート化されていて機械のなすがまま!!」
言葉の最後は嫌悪と軽蔑が入り交じり、冷たいものがあった。
「こめ都市はただ生きるためにそれだけのために機能しているんです。人間はここでは人形に過ぎない…」
言葉の途中でリネルのブレスレットが鳴った。リネルが耳を傾けた。
「トジアがあなたに会いたいそうです。朝食はそこで一緒にとって下さい。私の後をしっかりとついてきて下さい。ここは良く似たところしかないから。」
「Dr.チーラには会えるのかしら」
「チーラってだれ? そんな人は知らない。トジアだったら何か知っているかもしれない。とにかくトジアに会って下さい。」
敏子はリネルの後について部屋を出た。部屋の外は幅3mほどの廊下が一直線に走っておりその挟む壁には似たような扉がはり付いていた。この壁もやはり発光していた。リネルがブレスレットを何か調整すると、廊下の床の一部が強く輝いた。これをたどれば道に迷わないそうである。人に出会ったらどうするのかとたずねると
「ここではそんなことは起こりません。」
という機械的な冷たい声が返ってきた。この都市では他人と係わり合わないようにすることが個人の幸せの要件のひとつと信じられているそうである。プライベートではまず会うことはなく、マシンがすべての相手をしてくれるそうである。
細い廊下から一本の太い路に出た。人々はたしかに存在しているのだが、その存在ははかなく、今にも消え入りそうな感じがした。また彼女は均等な間隔をもって立っており、常に足元しか見ていなかった。これがこの世界を象徴していると敏子は思った。人々はMOVINGROADのうえにのっかりベルトコンべアにのっかるように運ばれている。
「MOVINGROADに乗ります。私の後について1Block後のに乗って下さい。」
とリネルが教えた。まずリネルが慣れた身のこなしでMOVINGROADに飛び乗り、後ろを向いて敏子が飛び乗るのを見ていた。敏子と言えばこんな物に乗るのは初めてである。エスカレーターの前でタイミングが取れずオロオロしている老婆のように踏ん切りがつかない。その間にリネルは少しづつ前の方に移動していく。敏子は焦った。焦ってどうしたかと言うとMOVINGROADと等速で走りだした。等速の慣性系では止まったように感じると言うことを応用したのである。
『我ながら頭が良い。』
とほくそえんで、次の瞬間、敏子は巌流島の宮本武蔵ばりの跳躍でMOVINGROADを目指した。…目指したのは良いのだがMOVINGROADの床の材質の摩擦係数の低さを計算に入れてなかったのが失敗で、それはもうこれ以上はないほどにあられもない姿でこけてしまった。腰をさすりながら-バツが悪そうに笑って-敏子は起き上がった。それを見ていたリネルは口のはしで笑った。そう悪役が主人公をいためつける前に見せるあの笑いである。敏子はむっとした。相手が本当におかしそうに笑っているのであれぼ一緒になって笑ってすませることができる。でもこの笑いではフォローのしようがない。敏子はむっとした。猛然とむっとした。恥ずかしさからの感情の転載をリネルに対する怒りとしてしまった。
『何よ、私だってこれに乗るの初めてなんだもん。そんな笑いかたしなくてもいいじゃない。』
とにかく自分は悪くなくて相手が悪い。[でも]と言う言葉を使って相手に罪をなすりつけ自己保全をするおばさん予備軍である質の悪い女子大生に見られる理論を頭の中で組立る敏子であった。一方的に都合の良い理論をたてた敏子の次の行動はと言うと、…。MOVINGROADを逆行して走りだしたのである。
『こんな女の言うことなんか聞くものか』
と言う呪文を口の中で唱えながら。元男の敏子である。それは普通の女性よりも脚力はある。ましてやほとんど走ったことのない都市育ちのリネルが敏子に追い付けるはずがない。リネルは敏子の後を追いながら左手のブレスレットに何か言った。敏子の前に二人の男が、それもすべてにおいて似ている二人が立ちはだかった。両手を開いてとおせんぼをしている。何を思ったか、敏子は自己紹介を始めた。リネルはまだずいぶん後である。
「私、浅田敏子です。あなたがたの名前は…」
「私はR-103」
と右側の方が律義にも答えた。すると左側の方が
「私の方がR-103」
だと答えた。右側の方が言った。
「製造プレートを見てもらえばわかるたしかにR-103と記してあるはずだ。」
左側の方は言った
「私の製造プレートはR-103だ。今、中央システムとの間で確認を取った。」
右側は言った。
「私も確認済みだ。」
どうしたわけかR-103が二人? 2体出現してしまった。2体が言い争っている間に敏子は再び2体を残して遂行し始めた。しかし走っても走っても周りに変化はなく、敏子は焦った。これでは話が進まない。でどうするかというと、ちゃんと作者はヒロインに愛の手を差し伸べております。ここで久しぶりのアンバー001の登場である。
『敏子さん、敏子さん。…』
頭の中で声が響いた。
「アンバーなの」
思わず叫んだ。ぽっと前上にアンバーが出現した。
「ようやく主人公の登場というところですね」
何か勘違いしているアンバーである。あきれた敏子ではあるがここでご機嫌を損ねたら厄介である。すがるように
「アンバー助けて」
と頼んだ。
「こちらです」
アンバーはMOVINGROADの脇の道の方に移動した。敏子も後についてMOVINGROADから降りた。今度は気張らずにうまく降りられた。
アンバーはしばらく進んで左手の方に折れた。そして5分くらい走っただろうか、ある部屋の前で止まった。追手はまだ見えない。
「この中に入って下さい」
アンバーがいった。敏子は少しためらってたずねた。
「あなた、メイ・シーンの処からどうやって逃げ出したの。」
「私にとってあんなトリック破るのは朝飯前なのですが、あそこのメイン・コンピューターにアクセスしてちょっと情報をもらっていたのです。姫に関することが何かわかるかもしれない。でも何も情報は得られなかった。」
気落ちしたようにアンバーが答えた。
「Dr.チーラは何処なの」
「彼なら心配はいりません」
と部屋の扉が開いた。中にはなつかしい顔があった。
「チーラ」
と叫んで敏子はその人物の方に身を投げ出した。アンバーが部屋に入り扉は再び閉じられた。
「チーラ、チーラ」
と敏子はチーラの腕の中で泣きじゃくった。
「敏子さん。良くご無事で」
チーラは敏子の肩を押し戻しながら顔をのぞき込んだ。
「あなたに、あなたに会いたかったの」
少女のように敏子は感情をぶつけた。チーラは背を向けて話し始めた。その態度はよそよそしかった。
「私はメイ・シーンの処に閉じ込められ、半ば終わりかなと絶望していました。そして私は一度死んだのです。」
それはショッキングな話だった。
「私は科学者であると同時に⛩教の司祭です。⛩教には司祭に代々受け継がれてきたある使命があるのです。そのため私は一度死んで再び以前のDr.チーラとは違った人格を持つものとして生まれたのです。」
敏子には何がなんだかさっぱりわからなかった。
「我が⛩教の開祖ソ・チーラは宇宙ステーション⛩から⛩星に移植するときの開発団の第1陣として惑星に降り立ちました。彼は生物学者であり、人間が生活可能であるようにその惑星の生物圏を確立することが仕事でした。彼は有能なスタッフと共にその仕事に成功をおさめたのです。そんなある日、彼は啓示を受けたのです。啓示というよりも使命を与えられました。その与えたものが何であるか彼は言及していません。その使命のため彼はある研究に着手したのです。個人の経験、知識を信号化しそれを蛋白質に乗せるという研究です。私達はその研究の成果というわけです。つまり、今の私は過去のチーラの人格も重ね持っているということなのです。」
話の途中にアンバーが割り込んだ。
「追手が追っています」
敏子は涙もぬぐわず虚脱状態に陥っていった。アンバーは発光している壁に向かって、可視光線を出力した。壁は円形に切り取られ、円の中には敏子達がのってきた船のコクピットが有った。
「さっ、早く」
アンバーの声と共にチーラは敏子を抱えるようにして円の中に飛び込んだ。コクピットの座席に座ると前方のスクリーンに開いている円が縮みだした。彼らがいた部屋の扉がダイダイ色に光り始めた。スクリーンの円は縮小していき最後にはようやく扉を壊し開いて乗り込んできたリネルの姿がちらっと見えて閉じてしまった。
TURBO氏より再指名を受け書くことになりました。私が入党する以前より続いていた大作なので責任をひしひしと感じておりますが、引き受けたからには好きかってさせていただきたいと思います。ということで話しは始まります。
さぁて話は思わぬ転回(展開?)を見せてきました。深まる謎、謎、ナゾ……。
どうやら話のkyeは⛩教の開祖ソ・チーラ氏に有るようです。と無責任に次回の予告をしてしまうのであった。
次回の作者の指名はMickey氏とさせていただきます。
著者の一言 後は野となれ山となれ
ワープロ入力者の一言 後悔先に立たず
|
|
|
|
|
|
|
Mickey 編
(1988年01月発行 Vol.59より)
|
|
|
|
さて、何とかアルテミラ星の政府庁をトジア・バジーナの部下の手助けで抜け出した敏子はアルテミラの地下都市セルスに連れてこられた。彼女敏子は更にトジア・バジーナからも逃げるためトジア・バジーナに会うために乗っていたMOVINGROADから飛び降りアンバーの協力もあり無事トジア・バジーナの手からも抜け出した。
敏子はアンバーにある部屋まで連れて行かれ、そこでチーラと再会したのであった。しかし再会を喜んでいる余裕はなくトジア・バジーナの追っ手を振り切るために自分達が乗ってきた船に戻ったのであった。
ここまでが前回のあらすじである。今回はここプロキシマ号の船内から始まるのであった。
「追っ手が来るわ。アンバー! 早く船を発進させて。」
「はい。はい。分かっておりますとも御主人様。いやいやお嬢様。」
ちょっとアンバーの調子がおかしくなっている。きっと私を救出するときに道に落ちていた腐りかけの食べ物でも食べたのだろうと敏子は思ったのであった。アンバーは非常に食い意地が張っているのである。
無事にアルテミラ星から飛び出し追っ手も来ないことをメインスクリーンで確認した敏子はチーラに尋ねた。
「あなたは本当にDr.チーラですの。さっきのセルスでの話がよく分からないのですが。私に分かるように簡単に話してもらえませんか。」
「それもそうでしょう。敏子さん 貴女が不思議に思われるのも当然です。先程は時間がなく充分に説明することが出来ませんでしたから。」
そこまでいうとチーラ博士はアンバーに飲み物を2つ持ってくるように言った。
「まず[私が本当にチーラか]ということですが私は間違いなくチーラです。⛩星一番の物理科学者で⛩教の宗主のチーラです。しかし貴女と⛩星を一緒に出たチーラではありません。」
言葉を選んでいるようにゆっくりとした口調で話し始めたチーラは一息つくかの様にアンバーが持ってきたコーヒーを飲んで再び話し始めた。
「私はほんの先程ア・チーラの死体から取り出された細胞からコ・チーラの手によって誕生したばかりなのです。[ア・チーラ]というのは貴女と⛩星を出たチーラで[コ・チーラ]というのはアルタミラ星に隠れ住んでいるもう一人のチーラです。私達は、私達とは私とアルタミラ星にいるチーラそしてMilky星にいるチーラの三人のチーラのことですが、」
ここまでチーラ博士が話すと敏子が
「うっそお-。Dr.チーラは4人もいたのぉ。」
と驚いたように言った。
「いいえ違います。私達はアルテミラ星、⛩星、Milky星にそれぞれ一人づつ3人います。そして誰かが死んだ場合に一番近いところにいる者が死んだ者の細胞から新しいチーラをつくるわけです。記憶や経験は細胞中の蛋白質に残っていますから記憶や経験が失われることはありません。その点からいえば私はア・チーラそのものになります。もっとも私が他のチーラを呼ぶときは[コ・チーラ][ド・チーラ]といい、私は[ア・チーラ]と呼ばれます。」
「ということは、前のチーラと変わっていないのね。」
いかにも嬉しそうな声を敏子は挙げたのであった。
「ところで、アルテミラ星のチーラさんは私に会った時に[我等一同貴女様の部下です。]っておかしなことをいったわ。ねぇチーラ、どういう意味かわかる?」
ちょっと首を傾けて言った。
「いや、なんのことだかわからないね。きっと君を誰かと間違えたんじゃないかな。あいつは少しおっちょこちょいなところがあるから。」
チーラ博士はなんでもないような口調で答えた。しかし心の中では
『まだ彼女の覚醒には時間がかかるみたいだな』
と思ったのであった。
「ねー、アンバーこの船もっと大きくならない。私眠くなっちゃったしぃ、洋服もぉ着替えたいしぃ。なんとかしてよぉ。」
アルテミラ星でのプリンセス扱いですっかり王女様気取りである。チーラ博士は呆れたような顔をして敏子とアンバーを交互に見ている。アンバーがどのようにするか見届けるためである。
「敏子さん、もうすぐ⛩星ですから我慢して下さいね。」
とアンバーは子供をなだめるかのように答えた。しかし敏子はがんとして聞かない。
「大きくしてよ」
「我慢して下さいよ」
の敏子とアンバーの押問答が何度となく続いた。しかし何度目のことだったろう今まで静寂を保っていたチーラ博士は
「アンバー、私からも頼むよ」
と静かだがどこかしらに力のある声で言った。
「博士にまで言われたのでは仕方がありません。分かりましたもっと大きな船に移りましょう。でも私が持っている船はこれしかありませんので博士、貴方が持っていたαケンタウリ号を使わせて下さい。」
「アンバー、なんでαケンタウリ号のことを知っているんだ。あれのことは誰も知らないはずなのに。」
「博士だめですよ。私は知っていますよ。なぜあの宇宙船があることを貴方が隠していたのかを。また、今何処にあるのかを。」
「なんだって。αケンタウリ号がいる場所がわかるというのか、アンバー」
「博士、貴方は」
突然、つまらなそうに敏子が
「敏子、つまんな-い。なんでもいいけど早く新しい宇宙船へ行こうよ。」
と口を挟んだ。
「とにかく、αケンタウリ号に向かいます。」
アンバーはこう言い終えるとプロキシマ号を小惑星どうしがぶつかりあいそうな空間に向かって進め始めた。実際、小惑星がぶつかるということはまずあり得ない話ではあるが。遠方から見るとぶつかりそうに見えるのである。
読者の皆さんにはアンバーが言おうとしていたことをこっそりとお教えしましょう。
αケンタウリ号とは⛩教の開祖ソ・チーラ氏が宇宙ステーション⛩から⛩星へ移住するときに用いた船である。この船には一般乗客として100人程度が乗り込めるが移住のときにはソ・チーラ氏と⛩教の信者の一部を運んだに過ぎなかった。なぜ信者の一部なのか、それは二回目の移住者を運んでいる途中に航行装置に異常をきたし乗組員は全て小型救助艇で脱出したのでそれ以後は別の宇宙船で移住が行われた為であった。乗組員を失ったαケンタウリ号は宇宙空間をさまようことになり初めは他の船の航行の安全性から船の位置を追跡していたが太陽の反対側にいったところから見失ってしまったのである。その後ふとしたことからαケンタウリ号を見付けたア・チーラ氏は緊急時の脱出用宇宙船として利用するために⛩星の付近にやってくるのを今や遅しと待っていたのであるがいま起きている空間の歪みの為にまたもや見失っていたのである。
なぜア・テーラ氏がαケンタケリ号の存在を隠していたか。それは現在⛩星で施行されている法律の為である。現在⛩星では個人で乗員10名を越える宇宙船を持つことは禁止されているのである。いくら⛩教の宗主であるア・チーラ氏でも法律を破るわけにはいかなかったのである。そのためαケンタウリ号が所有出来るように法律の改正を行なうように議員達に工作を行なっていたのである。
さて敏子、チーラ博士、アンバーを乗せたプロキシマ号は一路αケンタウリ号に向かって進んでいる。チーラ博士は銀河系政府の長官に現在の様子を聞くためと今までの報告をするために通信回線を開くようアンバーにいい、シークレット回線接続要請をおこなった。
「博士、シークレット回線接続のコードは何でしょう。」
「わしゃしらん」
「[わしゃしらん]って、そんなことはないでしょう。しっかり教えて下さいよ。」
「だから[わしゃしらん]といっておるだろうが。」
「博士いい加減にしておいてくださいよ。幾らおとなしい私でも怒りますよ[わしゃしらん]って、そんなことはないでしょう。」
(よくある話のパターンですみません。このまま続けても善いのですが何時までもやっていると話が続かなくなりますのでこの辺で終わりにします)
「だからコードは[わしゃしらん]といっておるだろうが。」
「わかりました。全くこんな回線接続のコードを考えたのは博士ですね。」
「アンバー、残念だったねこれを考えたのは私ではないのだ。考えたのは私の右腕として働いているミッキー君なんだ。」
「そのミッキーっていうのはよっぽど変わった男なんですね。博士、銀河系政府と回線が接続しました。なぜか知りませんが、ノイズがかなり含まれています。」
そういい終えるとアンバーは映像をメインスクリーンに写しだすようにした。メインスクリーンには長官の秘書らしい女性が出ている。コンサド長官の好みが伺える、どう見ても二十歳ぐらいにしか見えない女性だ。彼女は
「しばらくお待ち下さい。すぐにミオウ・コンドサ長官にお繋ぎ致します。」
なかなか丁寧ないいまわしである。おそらく教育係はクラッシャー氏が行なっているものであろう。クラッシヤー氏もたいへんだろうなと思いつつコンドサ長官が出てくるのをチーラ博士は待っていた。
「いやチーラ君、待たせたね。」
と異様に明るい声がスピーカーから聞こえてきた。聞き慣れた長官の声である。
「長官、其方の様子はいかがですか?。何か変わったことはありませんか。」
「別に特にないね。それより君が死んだという情報がこちらに伝わってきたのだがその様子から見ると情報は間違っていたようだね。証拠の品だといって君の死んだ姿の写真も一緒に送られていたようなんだ。」
「きっと何かの間違いでしょう。私はこのように生きていますからね。」
チーラ博士は極一部の人を除き誰にも自分の秘密をいっていないのであった。
「長官、アルテミラ星の調査ですが…」
と博士がアルテミラ星で見たことを話し始めた。報告が一通り終わると長官はチーラ博士に向かって話し始めた。
「博士、じつは惑星**でZ-80が***らしいんだ。」
「長官、なんですって。」
「惑星…」
「おいアンバー、どうしたんだ。」
「わかりません。回線が突然切断されました。」
宇宙船プロキシマ号の船内には重苦しい空気が垂れ始めました。突然の通信回線の切断。長官が言おうとしていたことはZ-80が見付かったのかそれとも盗まれたのか。見付かったとすれば何処なのであろうか。チーラ博士がつぶやいた敏子の覚醒とは。
謎はどんどん増えていきます。この謎を解くカギはどこにあるのでしょうか。ヒントを挙げましょう。カギを握っているのは敏子、クラッシヤー氏、ミッキー君さらにチーラ家の面々です。この続きは高校生のInk-pot君に御願いします。
|
|
|
|
|
|
|
絵夢絶人 編
(1985年10月27日発行 Vol.43「特別編」より)
|
|
|
|
(本文はありません:編)
野望と策略、そして愛、(アレッ、愛なんてあったっけ?)さらには、数多くの矛盾と収集のつかない問題を残しながらも、強引に進んで行くストーリー。
メイ・シーン VS トジア・バジーナ !! 二つの大きな勢力の狭間にチーラと敏子は活路を見出だす事が出来るのか? そして、アンバーは何をしているのか、行方知れずの王女はどこに??
スペクタクル・スペース・アクション・ロマン・ファンタジー・メルヘン・ミステリー小説、[連続大河小説]という名の連続大河小説、この後のストーリーはいかに……。
未来は今、貴方の手に…!
|
|
|
|
|